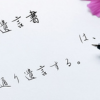第7章 年金関係の手続き

1.年金受給の停止と未支給年金の請求
(1)年金受給の停止
年金受給者が亡くなると、年金の受給は停止されます。そこで、「受給者死亡届(報告書)」を提出して、年金の受給を停止する必要があります。
受給停止手続きは、国民年金受給者の場合は14日以内、厚生年金受給者の場合は10日以内に、年金事務所や年金相談センターで行われます。
ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金のみを受けていた場合は、手続きは市役所で行う必要があります。
(2)未支給年金の請求(5年以内)
故人がまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族は、故人と生計を同じくしていた、配偶者⇒子⇒父母⇒孫⇒祖父母⇒兄弟姉妹⇒その他3親等内の親族の優先順位で受け取れます。
請求先は次のとおりです。
①市役所が請求先となる方
・国民年金の障害・遺族年金の受給権者が死亡した場合
・寡婦年金の受給権者が死亡した場合
②年金事務所または年金相談センターが請求先となる方
上記①以外の老齢・遺族・障害年金の受給権者が死亡した場合
未支給年金の請求には、生計が同一であったことを証する書面などの添付書類が必要ですので、事前にもよりの年金事務所または年金相談センターに確認してください。
2.遺族年金について(5年以内)
遺族年金とは、故人の所得で生計を維持していた遺族が受けられる年金です。遺族年金には、国民年金の「遺族基礎年金」と、厚生年金の「遺族厚生年金」があります。遺族がどの遺族年金を受けとれるかは、故人がどの被保険者に該当するかによって決まります。
(1)被保険者の種類
①自営業者など
⇒第1号被保険者(国民年金)
②会社員や公務員など
⇒第2号被保険者(国民年金&厚生年金)
③会社員や公務員の妻など
⇒第3号被保険者(国民年金)
1号と3号の加入期間だけの故人が亡くなった場合には、遺族基礎年金の支給対象です。2号の故人が亡くなった場合には、遺族基礎年金+遺族厚生年金の支給対象となります。
(2)支給要件

(3)支給対象者
 (4)支給額
(4)支給額

※遺族の妻が65歳前で「特別支給の老齢厚生年金(特齢厚)」を受給していた場合、この特齢厚と、亡くなった夫の遺族厚生年金額の選択という問題があります。
65歳前は、年金は1つしかもらえません。そこで、65歳前には妻自身の特齢厚と夫の遺族厚生年金の年金額を比較し、どちらか多い方を選択します。
65歳以降は、妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を全額もらいます。その上で、妻の老齢厚生年金よりも本来もらうべき夫の遺族厚生年金のほうが多い場合は、その差額分を遺族厚生年金としてもらいます。
(5)請求手続き行う場所
提出先は、遺族基礎年金の場合は、市役所(死亡日が第3号被保険者期間中なら年金事務所または年金相談センター)、遺族厚生年金の場合は、年金事務所または年金相談センターとなります。
3.寡婦年金・死亡一時金
寡婦年金は、亡くなった配偶者が社会保険や年金制度に加入していた場合に、配偶者が死亡した後に支給される年金の一種です。配偶者の死後、寡婦(もしくは寡夫)が生活費や生活維持に必要な経済的な支援を受けるために支給されます。
死亡一時金は、亡くなった人の遺族に対して支払われる一時的な給付金です。主に生命保険や労災保険、自動車保険などの保険契約に基づいて支給されることがあります。亡くなった人が保険に加入していた場合、死亡によって特定の条件が満たされると、その保険契約に基づいて遺族に一時金が支払われることになります。
 4.児童福祉年金(身体・知的・精神)を受給していた場合
4.児童福祉年金(身体・知的・精神)を受給していた場合
市役所に死亡の届出が必要です。また、1(2)と同様に、故人がまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
5.心身障害者扶養共済制度に加入していた場合
故人が心身障害者扶養共済制度の加入者であった場合、下記の要件に該当すると年金や弔慰金が支給される場合があります。なお、請求先は、加入している政令市の市役所か県庁です。
(1)年金
扶養共済制度の加入者(保護者)が亡くなった場合、対象の障害がある方に対し支給されるます。
(2)弔慰金
扶養共済制度に加入中(1年以上)に、対象の障害がある方が亡くなった場合、加入者(保護者)に対し支給されます。
6.災害遺児教育年金制度に加入していた場合
災害等により亡くなられた方が災害遺児教育年金制度に加入していた場合、死亡の届出により年金が支給されます。なお、請求先は市役所です。
7.農業者年金の加入者もしくは 受給者であった場合
故人が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として故人と生計同一であった遺族に支給されます。
また、1(2)と同様に、故人がまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
詳しくは、お近くのJAまたは農業委員会で確認してださい。
⇧はじめに戻る